張り詰めた空気の中、正眼の構えを取る相手を正面に置く。
こちらも同じように構えたまま、いつ攻められてもいいように精神を集中した。
一つ呼吸をする度、自らの意識が研ぎ澄まされていく。
緊張しているのか、相手は明らかに動きがぎこちない。
「……だあー!」
その鈍さを修正出来ないまま、大きく踏み込んできた。
馬鹿正直に突っ込むだけの、不用意な一撃。
大振りに迫る竹刀を横に払い、その勢いのまま自らの得物を相手の顔面に叩き付けた。
「あいたっ」
間抜けな声を漏らして、面を入れた相手がその場にすっ転ぶ。何をやっているんだこいつは……。
「それまで。今日はこのくらいにしましょう、二人とも」
横で見ていた叔父さんがパンと手を打って言った。
「はい! 夏輝さん、ありがとうございました!」
面の下から、明るい笑顔がひょこっと出てくる。
こいつは、つい最近叔父さんの剣術道場に入門してきた新米だ。
元気がいいだけが取り柄で、はっきり言って剣の才能は全くないように思える。
良くも悪くも素直なので、相手をしていて不快にはならないのだけが救いだった。
「気にしなくていい。それよりお前、もう少しフェイントを入れるか何かしろ。あんな一直線に突っ込んでも、多少心得のある相手には通用しないぞ」
「わかりました! ご指導ありがとうございます!」
深々と頭を下げてくる。返事だけは一人前だが、本当にわかってんだろうな……?
そう思っている間に、そいつは叔父さんに挨拶を済ませて帰ってしまった。
「お疲れ様です、夏輝。すみませんね、入門したての子の指導をお願いしてしまって」
オレの方に歩み寄ってきた叔父さんが、申し訳無さそうに言った。
「別に、構いませんよ」
本当は叔父さんに指導してほしかったが、練習生はオレだけではないから仕方がない。
それに叔父さんには、両親を亡くしてから親戚中をたらい回しにされていたところを引き取ってもらったという大恩がある。
そんな人から頼みごとをされたら、断ろうなどとは欠片も思わなかった。
「では、私は少し出かけてきますね」
「どちらに行かれるのですか?」
「津久井くんの告別式に参列してきます」
津久井……数日前まで、この道場で顔を合わせていた門下生の一人だ。
いつも無愛想なはずのオレのことをなぜか慕っている様子で、常に笑顔を絶やさない素直な奴だったのを覚えている。
「交通事故、でしたよね」
「……ええ」
オレの問いに、叔父さんは小さく頷いた。
はっきり明言しないのは、オレの母の死因も交通事故だからだろう。
その気遣いはありがたくもあり、ほんの僅か寂しくも感じる。
「オレは留守番をしてますから。安心して行ってきてください」
「そうですか……。わかりました。行ってきますね」
一瞬何か言いよどんで、叔父さんは出ていった。
来なくていいのか――そう言おうとしていたのはわかったが、あえて気付かない振りをして、叔父さんも結局口をしなかった。
まだ叔父さんに引き取ってもらってからそこまで経っていないのだから、この程度の遠慮は当たり前だ。
引き取ってもらっただけでなく、学園への転入の手続きをしてもらった上に、剣の手ほどきまでしてくれているのだから、これ以上を求めるのは筋違いだ。
それはわかっている。
それなのに、物足りなく感じてしまう。
もっとはっきり、自分に意見を言ってほしい、叱ってほしい。そう思う自分がいる。
(お母さん……)
オレのことをちゃんと叱ってくれていた人は、もうこの世にはいない。
シンと静まり返った道場が、やけに冷たく感じる。
「……早く掃除を終わらせて、夕食の支度でもするか」
込み上げてきたものを振り払うように、あえて大きな声を出した。
こんな寂しさにも、負けたりなんてするものか。
強くなってやる。一人でもやっていけるように。
強くなってやる。何があっても負けないように。
強く、なってやる。
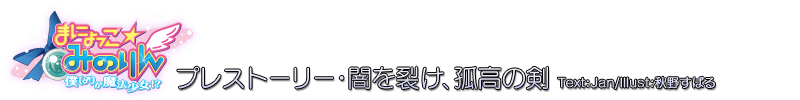
■01
■index■01■