帰りのホームルームが終わると、一つ仕事を終えたような気分になる。
特に長居する理由もないので、荷物を持って教室を出た。
最低限のものしか入っていないはずなのに、真新しい鞄は妙に重い。
転入直後はクラスの奴らが、珍しいものを見るような目で群がってきたが、それも最近では全くなくなった。
興味がなくなったというよりは、当初からオレが無愛想な態度を続けていたからだろう。
しかし、後悔はしていない。友達を作ろうなどとは最初から思っていないのだから。
未だに話しかけてくるのは、叔父さんの道場で一緒に修練に励む門下生たちくらいだが、
叔父さんの道場はお世辞にも流行っているとは言えず、他の門下生と滅多に学園内で顔を合わせることはなかった。
数少ない例外は……津久井くらいだった。
「それじゃ週末に映画館の前で待ち合わせだね」
「はい。ちゃんと貸した服を着てきてくださいね」
「うう……わ、わかってるよ……」
廊下に出ると、そんな会話が聞こえてきた。
羨ましくないと言えば、嘘になる。そんな触れ合い、オレには必要ないのに。
『神田さん、なにしょげた顔してるんですか?』
「……っ!?」
そんな声が聞こえた気がして、思わず辺りを見回す。
しかし、声の主――津久井はどこにも見当たらない。
当たり前だ。奴は、死んだのだから。
思っている以上に、津久井の死に動揺している自分に気付いて、思わず溜息をつく。
映画館。待ち合わせ。どちらも自分には縁遠い言葉だ。
最後にそれらについて話したのは、やはり津久井に遊びに誘われたときのことだった。
なぜかあいつは道場だけでなく、学園内でもわざわざオレのところへやってきて、一緒に昼食を食べようとか、
週末どこかへ遊びに行こうとか、飽きもせずに話しかけてきた。
あのときは鬱陶しく思っていたが……こんなことになるなら、一度くらい行ってやっても良かったかもしれない。
今更そう思ったところでどうしようもないのはわかっていたが、ついそんなことを考えてしまった。
(……線香くらいは、あげてやろうか)
そう思ったのも、オレ自身の弱さのせいなのかもしれない。
とはいえ、僅かな間でも同門生だったのだから、一度も行かないのは失礼にあたるだろう。
そんな言い訳を自分にしながら校外へ出ると、既に日は傾きかけていた。
自分と同じく家路を辿る生徒たちに紛れて歩き出す。
最初は嫌でも他の学園生の姿を見かけたが、十五分も歩くと、自分以外に歩いている人も見なくなった。
夕食にはまだ早い時間なので、ちょうど誰も出歩いていない時間帯なのだろう。
そうは思うのだが……。
(気のせい……か?)
不審に思われない程度に、辺りを見回してみる。
しかし、やはり自分以外に人影は見当たらない。
それなのに、どこからか視線を感じる。
普通なら気付かない程度の微かな気配だが、オレは昔からこういった感覚が鋭かった。
嫌な予感や不安感は覚えないが、一応確かめておくか。
ちょうど曲がり角に差しかかったので、曲がったところでぴたりと立ち止まる。
数秒置いてから踵を返して、曲がり角の向こうを覗き込んだ。
「きゃっ」
そこで鉢合わせたのは、純白の猫だった。
オッドアイを真ん丸にしてオレをじっと見つめてきている。
辺りを軽く見回してみるが、特に際立った気配は感じない。
どうやらさっきから後をつけていたのはこいつのようだ。
気配の正体が猫ならば、人影がどこにも見当たらないのも当たり前だ。
一つ疑問が解決したところで、思考を次へと移す。
……こいつ、さっき一瞬喋らなかったか?
「おい、オレに何か用か?」
真っ直ぐこちらを見上げたままの白猫に、そう声をかけてみる。
傍から見ると、猫に話しかける痛い奴に思われるに違いない。
オレ自身、常識的に考えて、猫が喋るなんてありえないと思う。
だが、そんな常識よりもオレは、自分自身が見聞きしたものを信じるようにしている。
さっき喋ったように聞こえたのが、オレの聞き違いならそれでよし。
そうでないなら、それはそのときに考える。
とにかく、問題を放置しておくのが性に合わないのだ。
「なあ、さっき一瞬喋らなかったか? 答えてみろよ」
はて、と白猫は首を傾げてみせる。
そうしてから、くるりとオレに背を向けて立ち去ろうとした。
咄嗟に足を踏み出して、白猫を後ろから抱きかかえた。
「逃げようとしてんじゃねえよ」
オレの疑惑はますます大きくなる。
なぜなら、こいつは猫のくせに、オレの質問に対してきっちり反応してみせた。
「……オレの言ってること、マジでわかってんじゃねえのか、お前」
「……にゃあ?」
無理矢理オレの方を向かせて問い詰めてみる。
当たり前だが、返答はない。が、この程度ではまだ納得は出来ない。
こうなったら最終手段だ。
意を決したオレは――白猫の腹の辺りを、わしゃわしゃとくすぐってやった。
ビククンッ! と身を震わせたかと思うと、白猫は手足を激しくばたつかせてオレの拘束から逃れようとする。
しかし、両手で抱え込むようにしているので、そう簡単に逃がしたりはしない。
そして、数分が経った頃だった。
「――すっ、すみませっ、あははははっ! ごしょ、後生ですからっ! 離してくだ、ひっ、あはっ、あはは!」
「……うおおっ!?」
突然人語を話し始めた白猫を、思わず放り投げてしまった。
この野郎……『やっぱりオレの勘違いだったのかな』と思い始めた頃に降参するんじゃねえよ。
「けほっ、けほ、ひ、ひどいじゃないですか。あれだけくすぐってきた上に、投げたりするなんて」
空中でくるくると回転して、見事に足から着地した白猫は、恨みがましそうな目でじとりと睨んでくる。
「ね、猫が喋ってやがる……マジかよ……」
「え……確信犯じゃなかったんですか?」
「勘違いだったかと思い始めてたところだったんだよ」
「ってことは、危うく私はくすぐられ損だったわけですか……」
深い溜息をつく白猫。
怪しまれるようなことをしていたのはこいつの方だから、こんな風に言われる筋合いはないのだが。
「お前がオレの後をつけてくるのが悪い。つーか、オレに何の用だよ、化け猫」
「ばっ……!? 化け猫だなんてひどいです! 私にはちゃんとミアって名前があるんですよ、夏輝さん!」
「……どうしてオレの名前を知ってるんだよ」
オレがそう言うと、白猫は目を丸くして、小首を傾げた。
「そういえば、どうして知っているんでしょう……?」
「知るか」
同じ質問を返されても、答えられるわけがない。
「なぜかわかりませんけど、当たり前みたいにわかったんです。ひょっとして以前どこかでお会いしていましたか?」
「オレは覚えてないぞ」
「私も覚えてませんが」
じゃあ聞いてくるな、と言いそうになる。
このいちいち相手に語りかけてくる話し方……似ているな。
今はもういないあの人に、よく似ている。
「ところで、結局お前は何者なんだ? どうしてオレをつけ回してたんだよ」
「そうですね、説明させてもらいます」
こほん、と軽く咳払いをしてから、白猫は真っ直ぐにオレを見上げて口を開いた。
「改めまして、私はミアといいます。天上の世界アルカディアにあるエデン担当の、いわゆる天使です。以後、お見知りおきを」
「は? 天使?」
「はい。ほら、可愛らしい羽もちゃんとついてます」
にっこり笑って、白猫――ミアは、その場でくるっとターンして見せた。
しかし、突然そんなことを言われても冗談としか思えない。
まったく、天使だというのなら、ちゃんと頭の輪っかを忘れないでもらいたいものだ。
とはいえ、こいつが人語を解しているのは事実なので、否定は出来なかった。
「その天使がオレに何の用だよ」
「ええと、私がいたアルカディアは、わかりやすく言うと死後の世界なんです。こちらの世界で命を落とした人の魂の向かう先、それがアルカディア。そしてそのアルカディアは、エデンとタルタロスの二つから成り立っている世界なのです」
「エデンにタルタロス……名前から察するに、天国と地獄か」
「そういうことですね。次の生を受けるまでの間、魂はそこで過ごすはずなのですが……ちょっとした不手際で、タルタロスにいた魂がこちらの世界に逃げてきてしまったんです。私はその魂――ガイストを回収するために、こちらの世界に下りてきたんですよ」
なるほど。わからん。
聞けば聞くほどファンタジーだ。こんな話を聞かされて、すぐに信じ込んでしまう奴の頭は、間違いなくお花畑だろう。
オレも普段だったらまるで信じていなかったに違いない。
その話をしているのが、喋る猫でなかったなら。
「で、それがどうしてオレをつけ回す行動に繋がるんだ? オレがその問題に関係してるとは思えないんだが。心当たりもない」
いわゆる霊感といった感覚は人一倍あると自負しているが、ここ最近は妙な悪寒を感じたりすることもない。
津久井の奴が命を落とした以外は、平和なものだ。
「あの、ですね。私たち天使は、実際には肉体を持ちません。でもこちらの世界では肉体がないと物に触ることすら出来ないので、不便なんです。だから今は、自分の魔力のほとんどを使って肉体を具現化させているんですよ。ただ、そのせいで本来の力を発揮出来ないんです」
「ここにいる時点で、お前らにはある程度の制約が課されてるってことか」
「ですから、私たちはこちらの世界で、パートナーとして協力してくれる相手を一人だけ付けてもいい、ということになっているんです」
そう言いながら、ミアはすがるような目で見上げてくる。
その視線の意図に気付かないほど、オレも鈍感ではない。
「どうしてオレなんだよ。オレは特別な力もない一般人だぞ。普通より感覚は鋭いかもしれねえけどな」
「その感覚の鋭さは、あなたの持っている魔力からくるものです。それこそが重要なんですよ。ある程度の魔力がないと、私たちのパートナーは務まりませんから。どうでしょう、ご助力願えませんか?」
「断る」
「ええっ!」
「そんな怪しい話に簡単に乗るバカはいない」
「そ、そんなあ……信じて頂けないんですか?」
「そういうわけじゃないが……」
ミアの口調や、オレを見上げる視線に偽りの色は感じない。
だが、協力するかどうかは別問題だ。
「それに、魔力がどうとか言うが、オレに特別な力はないぞ」
「それは大丈夫です。私と契約を結んで頂ければ、夏輝さんが持っている魔力を魔法として行使出来るようになりますから」
「フン、なるほどな。そうやってこちらの世界でパートナーを見つけるわけか」
「そういうことです。ですから夏輝さん。私と契約を結んで、魔法少女になってください!」
「……は?」
「ですから、魔法少女になっていただければと……」
「天に還れクソ猫」
背を向けてその場から歩き出す。
「わー! ま、待ってくださいー!」
「待たねえよ! ついてくんな! パートナーは他に探せ! つーかオレは男だ!」
ちゃんと話を聞かなければよかった。時間を浪費してしまった感が否めない。
男のオレに「魔法少女になってくれ」とは、何を勘違いしているのか。
話している感じでは、こいつの性格は真面目で、嘘がつけない馬鹿正直。
だからオレを馬鹿にしているわけではない、というのはわかる。
わかる、が……だからといって、それを笑って許せるほどオレも大人ではない。
「あなたが男なのは百も承知です! でも、一目見たときにピンときたんです。『私のパートナーはこの人しかいない』って……お願いします、あなたの力が私には必要なんです! それに、あなたほどの力があれば、きっと……」
「うるせえな……それがオレに何の関係がある。てめえの事情おしつけてくんじゃ……、っ!?」
唐突に悪寒を覚えて、反射的に振り返る。
視界には人影どころか、動く物すら映らない。
物音もなく、誰かがいるような気配もまるで感じられなかった。
全身の産毛が逆立ったかと錯覚するほどの強烈な不安感、その余韻だけが、オレの胸を内側から叩いている。
「夏輝さん、突然どうかしましたか……?」
「……いや、なんでもない」
気のせいだ。というより、気のせいだと思いたかった。
見てはいけない何かがそこにいたような、そんな気配があった。
その恐れを振り払うように、オレの足は自然と速まるのだった。
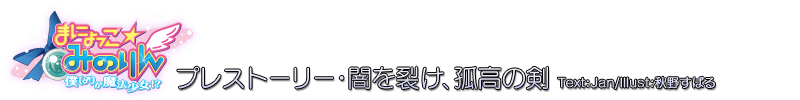
■02