家に帰ると、オレはいつものように夕食の準備に取り掛かった。
叔父さんは落ち着いていて、人に気配りも出来る人格者で、剣の腕前も抜群だが、家事の類――それも、特に料理はあまり得意ではないのだった。
白いご飯に、出来合いの惣菜を付け、それにインスタント味噌汁……といった献立はまだいい方で、ひどいときには、三食とも素うどんを食べていたりもした。
さすがに見るに見かねて、オレが料理当番を申し出たのは、つい最近のことだ。
「おかえりなさい、夏輝。いつもすみませんね」
そろそろ出来上がるという頃になって、道場の方から叔父さんがやってくる。
家事を受け持つことになった関係で、平日は夕食後にしか剣の稽古をつけてもらえなくなったが、仕方のないことだ。
「叔父さんにはいつもお世話になってますから、気にしないでくださいよ」
「そうですか。でも助かりますよ。ふむ、この匂いは……今日は焼き魚ですか。夏輝は魚が好きなんですね」
「昔から肉より魚の方が好きだったんです。母が魚好きだったのが移ったのかもしれませんね」
言いながら、焼き上がった魚を皿に載せ、並行して作っていた味噌汁を二人分用意する。
事前に炊いておいたご飯を二つ盛って、あとは先日食べ残した煮物と漬物を食卓へ並べて終わりだ。
「いやあ、今日も豪勢ですね。では、いただきます」
食卓についた叔父さんが嬉しそうな顔で言った。
「普通ですよ。叔父さんの普段の食生活が質素すぎるんです。お言葉ですが、改善の必要があると思います」
「はっはっは、恥ずかしい限りですよ」
まったくこの人は……こういうところがなければ、もっと尊敬出来るのに。
そう思いながらも、つい口元が緩んでしまう。
記憶の中にだけぼんやりと残っている、温かな食卓――。
それをまた囲うことが出来るのは、この人のおかげだ。
それだけのことが、どれだけオレを救ってくれているか。
こんな食事を振舞う程度のことは、百回繰り返したとしても、恩返しには全く不十分だろう。
「ところで夏輝。今の学園に転校してしばらく経ちますが、上手くやれていますか?」
「ええ、何も問題はありません」
嘘ではないので、淀みなく答えることが出来た。
が、叔父さんは語調を変えないまま、更に踏み込んでくる。
「友達は出来ましたか?」
「…………」
持っていた茶碗と箸を置いて、口の中のものを咀嚼する。
なんとなく叔父さんの方を見られないまま、口を開く。
「……いいえ。ですが、友達なんて必要ありません。無理に作る必要もないと感じますし」
「夏輝。友人は作るものではありません。自然と、そうなっているものです。あなたがそう言っていても、近いうちにきっと友人と呼べる相手が出来ていますよ」
不意に、ほんの最近まで一緒に修練を重ねていた後輩の笑顔が脳裏に浮かんだ。
友人は作るものではなく、自然とそうなっているもの……確かに、そうかもしれない。
ただ、唯一友人と呼べたかもしれない相手は、もうこの世にはいないが。
「ごちそうさまでした」
空になった椀と皿を流しに持っていき、ひとまず乾燥しないように水に漬けておく。
片付けは、後で叔父さんの分と合わせてまとめてやればいい。
居間に戻り、それとなく時計を確認する。
時刻は午後七時を軽く回ったところだった。
……行くならば、今くらいがぎりぎりだろう。
「叔父さん、少し外出してきます。遅くとも八時半頃には戻ると思いますので」
「ふむ」
ちらりと、細い目が僅かに見開いてオレを見た。
「あまり遅くならないように」
「はい、行って参ります」
あえて叔父さんが行き先を聞かなかったのは、叔父さんなりの心遣いだろう。
普段はその遠慮にも似た態度を寂しく思ったりもするが、今回ばかりはありがたかった。
家を出ると、もうすっかり日は傾いて、山の向こうへと沈みかけていた。
空には星が瞬き、薄い雲に覆われた月がぼんやりと辺りを照らしている。
津久井の家までは、徒歩で二十分少々かかる。
ぼやぼやしていないで早く向かおうと、足早に門を出た瞬間だった。
「こんばんは。また会いましたね」
突然の呼びかけに視線を向けると、白々しくにこにこと笑う白猫の姿がそこにあった。
一瞥だけして、オレは先を急ぐことにした。
叔父さんを心配させるわけにもいかない。
早く用事を済ませて帰らないとな。
「ちょ、ちょっと夏輝さん! 待ってくださいよ~!」
後ろをとてとてと慌てて追いかけてくるのが気配でわかる。
「……待ち伏せしておきながら、また会ったとか、白々しいにもほどがあんだろ」
「す、すみません。その、まだ伝えていないこともありましたから……」
深い溜息が漏れる。こういう諦めの悪い奴は悪気がない分、始末が悪い。
「何度も言うが、お前の事情なんてオレの知ったことじゃない。お前を助ける義理も理由もオレにはないだろ」
「ですが、メリットがないわけではありません」
その発言に、オレは足を止めた。
振り向いてミアに視線を向ける。
「どういうことだ?」
「ガイストは、魂だけの存在。こちらの世界にいるだけで、私たちと同じように魔力を消費し続けているんです。そして、彼らはその魔力を他の人から吸収出来ます。ですから、夏輝さんのように強い魔力を内在させている人は、ガイストの格好の餌食にされてしまう危険が高いんです。でも私と契約してもらえれば、魔法で対抗出来ます」
「そんなことか……相手がオレに干渉できるってことは、そいつらは肉体を持っているんだろ? こちらからも干渉出来るなら、問題ない。オレ自身の力で退けてみせる。魔法だかなんだか知らねえけど、いらねえよそんなの」
話を一方的に切り上げて、再び歩き出す。
万が一ミアと話しているところを誰かに見られて、『猫と話している痛い奴』なんて噂が立つのも望むところではない。
無駄な時間を使ってしまったな。早く津久井の家に行かなくては。
ミアのことを完全に置き去りにして、足を前へ前へ動かした。
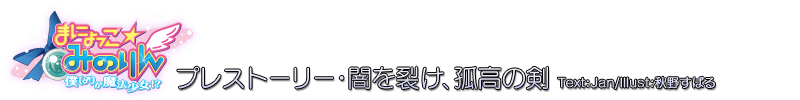
■03