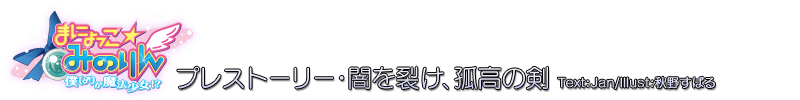年齢の割には若く見える容姿をしているが、腫れた目と無理に作った微笑みが、疲れているような印象を覚えさせる。
確か津久井は一人っ子だったはずだ。それが亡くなってしまったのだから、無理もない。
「この度はご愁傷様です。ご葬儀に参列出来ず、こんな時間の弔問となってしまい申し訳ありません」
線香を上げさせてもらってから、改めてお悔やみの言葉を告げる。
「気にしなくて大丈夫よ、神田・夏輝くん。あなたのことは、あの子からよく聞かされていたわ。こうして来てくれただけでも、きっとあの子も喜んでいるはずよ」
「あいつには、なぜかとても懐かれていましたね」
「あの子は、あなたに憧れていたみたいだったわ。大人しくて気弱だったあの子に良い影響があればと思って道場に通わせてから、帰ってくる度『神田さんはすごい』、『いつか神田さんみたいになる』って、大はしゃぎで……」
生前、オレとの稽古のときでも、津久井は似たようなことをよく言っていた。
明るくて真っ直ぐな笑顔を、無闇やたらにまき散らしながら。
オレはそんな津久井のことを鬱陶しく思いながら、奴のそういうところを決して嫌いになれなかった。
あの馬鹿が。何がオレみたいになる、だ。
それなら、事故なんかに遭ってんじゃねえよ……くそが。
「そうだわ。少し待っていて」
津久井の母親が、何か思い出したように顔を上げて、部屋を出て行った。
ほどなくして戻ってきた彼女が、あるものを持ってきていた。
「これは……」
それは、一振りの使い古された木刀だった。
柄の部分に『津久井』と名前が彫られている。
間違いない。津久井が道場で使っていたのと同じものだ。
「あの子が大事にしていたものだけど、よかったら使ってあげて」
「いいんですか? こんな大事なものを……」
「ええ。あなたに使ってもらえれば、あの子も喜ぶと思うの」
そこまで言われては、無下にすることも出来ない。
「わかりました。大切にさせて頂きます」
宝物でも受け取るかのように、両手でそっと持ち上げる。
日常的に振るっている道具のはずが、なぜだか普段よりもずっと重く感じられた。
「では、あまり遅くならないようにと言われていますし、おいとまさせて頂きます」
「そう。またいつでも来て頂戴ね」
「ありがとうございます。お邪魔致しました」
丁寧にお辞儀をしてから、オレは津久井の家を後にした。
手荷物が出来てしまったが、それと一緒に大きなものを託されたような気がする。
この木刀には、津久井の努力が、思い出が、魂が染み付いている。
それを譲られたことを、オレは素直に嬉しく思ってしまっていた。
同時に、気付かないでいようと思っていた切なさが込み上げてくる。
失ってから気付くなんて、オレもかなりの大馬鹿者だ。
込み上げた感情が目元から滲み出る前に、頭上の月を見上げた。
薄ぼんやりとした柔らかい光が余計に寂しさを募らせるが、そうしていないと、オレの弱さがこぼれてしまうのではないか。
そんな危惧があった。
「神田さん、なにしょげた顔してるんですか?」
だから、最初にその声を聞いたとき、オレはまた幻聴だと思った。
「やだなあ。無視しないでくださいよ。傷つくじゃありませんか」
雲の裂け目から、月の光が僅かに差し込む。
それに照らし出された、電柱の影。
そこにいるはずのない奴がいた。
いてはならない奴が立っていた。
「つく……い……?」
「こんばんは、神田さん。僕に会いに来てくれたんですね。あはは、ありがとうございます」
オレの知っている笑顔で、目の前のそいつはそう言った。
死んだ奴には、もう会えない。声も聞けない。それが当たり前だ。
いつものオレなら、実は津久井には双子の弟がいたとか、オレが夢を見ているとか、そういう可能性を考えただろう。
だが今は、違う。昨日までなら考慮にも値しなかった可能性が残っている。
――ちょっとした不手際で、タルタロスにいた魂がこちらの世界に逃げてきてしまったんです。
――私はその魂――ガイストを回収するために、こちらの世界に下りてきたんですよ。
ミアの言葉を思い出し、オレは自分を落ち着かせてから、目の前の津久井をしっかりと見据えた。
タルタロスがこちらの世界で言う地獄だとすると、こいつはどうやら地獄に堕ちたらしい。
恐らく、親よりも先に命を落としてしまったのが原因だろう。
昔、賽の川原という、親に先立って死んだ子供が堕とされる地獄の話を聞いたことがある。
その場所が実在するかどうかはわからないが、親より先に逝くことが罪であるのは確かなようだ。
「迷って出たか、この親不孝者のクソ馬鹿野郎が」
「相変わらず、ひどいなあ……僕だって、好きで死んだわけじゃないのに。まあ、あんまり実感ないんですが、自分の葬儀を見たら、信じないわけに行きませんよ。それに、父さんも母さんも、僕のことが見えてなかったみたいです。神田さんは僕のことがわかるみたいで、安心しました。神田さんに用がありましたから」
言い終わると同時に、津久井はどこからか木刀を取り出して、正眼に構えた。
「車にはねられて、意識が落ちる瞬間に思ったんです。死ぬ前に一度くらい、神田さんに勝ちたいって。神田さん。本当に僕のことを思うなら、最後の真剣勝負、受けてくださいよ」
「フン。一度もオレに勝ったことねえくせに、偉そうに……。言っとくが、同情して手抜きするなんて思うなよ」
「思ってませんよ。では、参ります!」
言うが早いか、津久井は躊躇なく一気に間合いに飛び込んできた。
踏み込みが早い。避けるのは無理だと判断し、持っていた木刀で振り下ろされた一撃を受ける。
「くっ……」
津久井は小柄だが、体重の乗った初撃は重く、受けた瞬間木刀を持つ手が痺れた。
真面目に修練を積んでいただけあって、振りが鋭い。
しかし、動きが素直すぎて、どこを狙っているか一目でわかってしまう。
力任せに木刀で押し返し、津久井の体を弾き飛ばした。
「とっと……」
バランスを崩した津久井がたたらを踏む。
僅か一秒程度の間だが、オレが攻撃に転じるには十分過ぎた。
奴が立て直す前に、木刀を右に払う。
津久井はオレの攻撃に反応したものの、体勢を崩していて脇が締まっていなかったので、腕ごと弾かれる結果となった。
無防備になったところに木刀を振り下ろそうと、腕に力を込めたとき、津久井の表情が一瞬目に入った。
明らかに負けが確定した瞬間だったはずなのに、奴は笑っていた。
オレの知っている明るい笑顔ではない。
まるで詐欺師のような、嫌らしい笑み。
「――がはっ!」
そして、木刀が叩き付けられた。
オレの脇腹に、細い刀身がめり込んでいた。
強烈な痛みに思わず持っていた木刀を取り落として、その場にうずくまる。
苦しい……息が上手く出来なくて、涙で視界がかすむ。
どういうことだ? なにが起きた?
オレは、相手の木刀を弾いてから攻撃したはずなのに、ありえない場所から木刀が飛んできた。
わけもわからず混乱するオレの耳に、津久井の愉快そうな声が聞こえてくる。
「さすがだなあ神田さんは。やっぱり奥の手を使わないと勝てなかったか」
「おく、の、て……?」
「奥の手というよりは、他の手って方が正しいかもですけどね」
なんとか顔を上げたオレは、目を丸くした。
「な、なんだよ、それ……お前、手が……っ」
津久井の背中からは、幾本もの手が生えていた。
イソギンチャクか何かのようなうねうねとした動きに、生理的な気持ち悪さを覚える。
さしものオレも、動揺を隠せなかった。
あの中の一つが、弾かれた木刀をその勢いのまま叩き付けてきたらしい。
「あは、あははは! やった、やったあ! 神田さんに勝ったぞ!」
「津久井……てめえ、そんな騙し討ちでオレに勝って、嬉しいのかよ」
「うるさい!」
背中から伸びてきた白い手が、触手のようにオレを拘束する。
細いくせに、物凄い力だ。ちょっとやそっとでは抜け出せそうにない。
「僕はあなたに勝ったんだ。だから、その体……好きにさせてもらいますよ」
にたりと笑った津久井に、生前の無邪気さは感じられない。
明らかに、オレの知っている奴とは何かが違う。
そんなことを考えていたら、突然複数の手が、オレの服を剥ぎ取りはじめた。
「なっ!? なにすんだ、てめえ!」
慌てて身をよじろうとするが、両腕と両足の辺りを強く押さえつけられているため、抵抗らしい抵抗も出来ないまま、服がはだけられていく。
素肌が晒されると、湿った夜の空気を直接感じてしまう。
半裸になったオレを見て、津久井はうっとりとした表情を浮かべながら、ほうと溜息をついた。
「神田さん、思った通り、すごくきれい……。無駄な肉がついてなくて、でも筋肉はちゃんとついてて……」
「か、解説してんじゃねえよ!」
かあっと顔が熱くなる。
男に見られること自体は恥ずかしくもなんともないが、こんなにも体をまじまじと見られると、さすがに羞恥が湧き起こってくる。
「おい、もういいだろ……とっとと離せよ」
「何言ってるんですか、ここからが本番じゃありませんか」
きょとんとした顔で、津久井は言った。
本番? 何の? いよいよこいつの意図が掴めず、首をかしげる。
そんなオレの心を見透かしたように、津久井は口元を吊り上げた。
「こんなおいしそうなものを目の前にして手をつけないなんて、男じゃありません」
「……ま、まさか」
オレの不安は、的中した。
津久井の手の一つが器用に制服の留め金を外して、ファスナーを下ろしてくる。
為すすべもなく、性器を引きずり出されてしまった。

「へえ、顔に似合わずご立派なんですね。これからもっと大きくなるんでしょう?」
言いながら、津久井はサオの部分を包むように握ってくる。
「っ! くあっ!」
瞬間、刺激の強さに腰がビクンとはねた。
自分で触るのと他人に触られるのでは、感じ方がまるで違う。
「感じやすいんですね。はは、神田さんってばかわいいなあ」
「ざけんな、あっ! ん、んううっ……そ、そこは、誰だって敏感だろうが」
「かもしれませんけど、それにしたって感じすぎじゃありませんか? もう手の中に収まりませんよ」
その言葉通り、ゆっくりとしごかれていただけなのに、オレのチ〇コはすっかり膨れ上がってしまっていた。
精神修行もそれなりにこなしてきたのに、オレの意思に反して、精一杯に自己主張をしている下半身。
情けなさと悔しさがブレンドされた恥ずかしさを誤魔化すように、一際大きな声を出そうと口を開く。
「これはただの生理現象だ! いい加減にしろ津久井! これ以上やると……んむぐっ!?」
セリフを遮るように、津久井の指が、口の中に侵入してきた。
顔の半分を掴むようにして、親指でオレの口内をこね回してくる。
舌が上手く動かせないから、これでは上手く喋られない……。
「静かにしてくださいよ。それとも、そんな恥ずかしい格好をしてるところを誰かに見られたいんですか?」
「……っ」
ならばと思い、あごに力を込める。
だが、歯が奴の指に食い込もうとしたと同時、
「んぐうううっ!!」
強烈な刺激が、チ〇コの先から全身にはしった。
いや、刺激というよりは、今のは最早痛みに近い。
突然のことだったので、思わず目を白黒させてしまう。
「おいたはダメですよ、神田さん。そういうことをしようとするなら、僕も乱暴にするしかなくなっちゃいます」
何かとがった感触が、亀頭に当たっている。
見ると、津久井はオレのチ〇コの先端に指先を触れさせていた。
さっきの感覚は、亀頭を爪で引っかかれたものだったようだ。
男である以上、そんなことをされたら無反応でいるなんて不可能だ。
これでは自分自身を人質に取られているようなもの。大人しくしているしかない。
オレから抵抗の意志が薄れたと見るや、津久井はにこりと笑顔になる。
「あの神田さんが僕の言いなりになってるなんて、ゾクゾクしちゃいますね」
言いながら、乱暴にいきり立ったオレ自身を擦ってくる。
更に他の腕が服をめくりあげて、中へと滑り込んできた。
その指先が肋骨をなぞりながら、胸の方へと上っていき、やがて乳首へと到達する。
小さな突起を優しくこねられると、甘い痺れがじんわりと起こった。
チ〇コに与えられる刺激に比べるとささやかなもので、逆にもどかしい。
「どうです? 気持ちいいですか? 指抜いてあげますから、答えてくださいよ」
津久井の親指が口内から引き抜かれる。
つうと唾液が透明な糸となって伸びたのが、やけに淫らに思えた。
「……全然よくないな。下手くそ」
「その割に、先っぽ濡れてきてますけど。ほら」
「うあ、う、っく……ああ!」
亀頭を指の腹で撫でられて、意に反して声が漏れてしまう。
先走り汁がくちゅくちゅと淫靡な音を立てて、それが羞恥心と屈辱感を煽ってくる。
「ほら、気持ちいいんじゃないですか。素直になりましょうよ」
「き、気持ちよくなんて、ない……」
ぐっと下唇を噛んで、全身を硬直させ、快感を拒もうと試みる。
「そんなに嫌がらなくたっていいじゃありませんか。これは生理現象なんですから」
「せいり、げんしょう……?」
確かに、相手が津久井でなかったとしても、こんな触られ方をしたら勃起は止められなかっただろう。
これは生理現象だから、仕方ない。
そうなのかも、しれない。
だから、気持ちよくなってしまうのだって、仕方がないことなんだ。
そんな甘い言葉が、徐々に思考を侵してくる。
「で、でも、お前なんかの手で気持ちよくなるのは、いや……んんあっ!? ああっ!」
喋っている最中なのに、痺れを切らしたのか、津久井は手コキを再開した。
「はあ、ま、待って……ひぅっ! 人の話を、聞けよぉ!」
「だって神田さん、素直じゃありませんから。おち〇ちんは素直なんですけどね」
親指と人差し指で作った輪で、カリの辺りをこすこすと刺激される。
腰が僅かに浮いてしまい、唇から熱い吐息が漏れた。
「すごい、ピクピクしてますね。神田さん、普段オナニーとかしないんですか?」
「んなもん、しねえよ……っ」
そういった一人遊びの経験がないわけではないが、ここ最近はその気が起こらず、ご無沙汰だった。
そのせいか、自分で思っている以上に、小さな刺激で過剰なまでに反応してしまう。
こすられる度に滲み出るカウパーが、入り口から垂れて陰茎をてらてらと光らせる。
「はぁ、はぁ、ふぁ、あ、ん……ッ」
肉棒の根元で、己の欲望が溢れ出そうと暴れ出そうとしている。
ぐるぐると袋の中で巡り巡って、出口へと向かってせりあがってきているのを感じた。
これ以上されたら、本当に……!
「も、もうやめろ、津久井。今回は素直に負けを認めるから、だから……」
「何言ってるんですか? 中途半端なんて、らしくないですよ」
ニヤリと嗜虐的な笑みになって、絶望的な宣告がされる。
「最後までちゃんとイカせてあげますからね」
「や、やめろおぉぉっ! あっ! うあああっ!」
全身に力を込めて拘束を解こうとするが、押さえつける力は緩むことすらない。
こいつ、本当にオレを絶頂にまで導くつもりだ。
それだけは、そんな恥ずかしいのはいやだ。
その思いを踏みにじるように、体を弄ぶ手の動きは激しさを増していく。
「ん、ンッ、ンフゥゥッ! は、はああっ、もう、やめっ、んはァァッ!」
すっかり目覚めさせられた性の衝動を抑えられず、艶かしい喘ぎが溢れてしまう。
涼やかな夜の空気に晒されているはずの肌の火照りはまるで冷めることなく、じっとりと汗ばんでいた。
「くぅうう! もう本当に、出ちまうっ! から、やめっ……」
「やめませんってば。我慢してると苦しいでしょう? 手伝ってあげますから、どうぞイッてくださいよ」
津久井の腕の一つが下の方から忍び寄ってくる。
そして、ぐにゅりと、ふぐりを鷲掴みにした。
「ひがあああっ!? ああっ!? なにすっ、ひゅぐううぅぅうう!!」
玉袋を握った手が、そのままもみもみとマッサージしてくる。
中に詰まっている白い欲望を搾り出そうと、執拗に責め立ててくる。
もう我慢の限界だった。
射精せずに済んでいるのは、やせ我慢が最後の一線で踏み止まっているに過ぎない。
「我慢強いなあ、神田さんは。そうだなあ、多分この辺りかな?」
まるで探るように動いた津久井の指が、今まで触れられなかった裏スジへと伸びた。
カウパーでぬるぬるになったそこを、無邪気ゆえの容赦のなさでこすりあげる。
「――っ!?」
途端に、呼吸が止まる。いや、時間が止まったような感じがした。
目の前がフラッシュして、何も感じられなくなる。
「あ、あっ……」
その直後、オレ自身は決壊した。
「ああああああああああっっ!! ふああああああああーーッ!!」
我慢に我慢を重ねた上での、絶頂。
それはまるで、オレ自身が壊れてしまうのでは、そう思わせるほどの衝撃だった。
「かっ、あがああっ! ひゃめ、とまら、あああっ……ふああ……あッ……!」
信じられないほど大量の精液が、噴水のように飛び散る。
頭の中が、真っ白になる……。
き、もち、いい……。
その一瞬、オレは恥ずかしさも忘れて、ただただ快楽の余韻に身を浸らせてしまっていた。