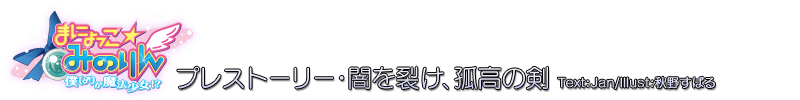結局、津久井に、後輩にイカされてしまった……。
こんなに屈辱的なことはない。
我に返ったオレは、ぎり、と強く歯をきしませる。
「あはあ……これが、神田さんのお汁ですか……」
うっとりとした表情で、津久井は手にかかったオレの精液をまじまじと見つめていた。
かと思うと、おもむろに舌でぺろりと舐め取る。
「すごい、濃厚でおいしい……もっと、もっとくださいよ、神田さん」
「も、もっとって」
まだ終わりじゃないのか? いくらなんでも冗談になっていない。
「こんな機会、もう二度とないかもしれませんからね。一回で終わりなんて、もったいないです」
「ふ、ふざけんな! とっとと離せよ!」
腕から逃れようとするが、絶頂の余韻が残る体からは力が抜けてしまっていて、ほとんど身動きも取れない。
このままじゃ、またこいつにイカされてしまう。
どうしようもないのか……そう思った、そのときだった。
「スペル、クイックスキャット!」
視界の端から現れた白い影が、津久井に向かって猛烈な勢いで飛びかかった。
直後、オレの耳に、ザシュッ、と鋭い音が届く。
「いっ……ぎゃああああッッ! 目が、僕の目があああ!!」
顔面を押さえてよろめく津久井。
そのおかげか、オレを拘束する腕から力が抜けた。
ここしかない。腹筋に力を入れて、地面を転がるようにしながら腕の拘束を振り払う。
「大丈夫ですか、夏輝さん!?」
津久井を襲った白い影――ミアが心配そうに見上げてきた。
「ああ、なんとかな……礼は言っとく」
「どういたしまして。あの人の目元を引っ掻きましたから、視界が戻るまでには時間がかかるはずです」
津久井の苦しみようは尋常ではないと思ったが、ミアのそのセリフで合点がいった。
目を直接引っかかれたりしたら、ああなるのも無理はない。
下手をすると失明もありうる。こいつ、とぼけた顔してなかなかえぐいことをする奴だな。
「さあ、今の内に逃げましょう」
「いや……逃げない」
「え? な、なぜですか?」
「あいつ、ガイストなんだろ。それならここで倒した方が、お前にとって都合がいいはず。違うか?」
「そ、それはそうですけど、夏輝さんを危険に晒せません! 生身の人間が勝てる相手じゃありませんし……。夏輝さんだって、それを肌で感じたのではないですか?」
ミアの言う通り、津久井の力は生前とは比べ物にならないほど高まっていた。
完璧なタイミングで振るったはずの一撃も簡単にかわされたことから、オレが勝つ確率がほとんどないことは明らかだ。
そもそも、今の津久井には幾本もの腕があり、それを回避する術がオレにはない。
戦ったとしても、またすぐに拘束されて終わり……そんな結末が待っているのは明白だ。
それでも、オレは……。
「あいつは、オレの後輩で……友達だったかもしれない奴なんだよ。だからオレが介錯してやりたいんだ」
「な、ならせめて、私と契約してからにしてください! それならきっと勝てますから!」
その言葉に、オレは小さく首を横に振る。
「オレだけの力でやりたいんだ。お前の力は借りない」
両親を亡くしてから、オレは誓った。
誰にも頼らず、たった一人で強くなろうと。
そのために剣を習い、精神修行にも励んできた。
それなのに、津久井にすっかりいいようにされてしまった。
この汚名を返上するためにも、目の前の敵は自分だけの力で倒さねばならない。
たとえそれが無謀としか思えない行為でも……そう思って意志を固めた、まさにその瞬間だった。
「い――いい加減にしなさい!!」
目の覚めるような大声に、驚いたオレは、ミアに視線を落とした。
「そうやって他人を拒んで、自分も周りも傷つけて、心配ばかりさせて! 勝手ですよ! それで何を得られるというのですか。あなたの望む未来が手に入るのですか?」
その問いに、オレは黙り込むしかなかった。
自分の行為が単なるわがままで、自分勝手だということを、オレ自身、わかっていたからだ。
でも、それを認めてしまうと、今までやってきたことを自分から否定してしまうような気がして、オレはミアの問いに、イエスともノーとも言えなかった。
「あなた自身のためにも、お友達のためにも、強がるばかりではいけませんよ」
誰かに叱られるなんて、一体何年振りのことだろう。
その感覚が、なぜかひどく懐かしく思えた。
オレを叱る人間は、もうこの世にはいない。
しかし、この小さな白猫に、なぜかその人の面影を見て、フッと笑みがこぼれた。
「オレは、借りたものはちゃんと返す主義だ」
言葉の色がわからないのか、ミアが目を丸くする。
それに構わず、言葉を続けた。
「さっきお前はオレを助けてくれたな。その恩は、きっちり返す。お前と――契約してやるよ」
「あ……はい! では、この指輪をはめてください!」
ぱあっと顔を輝かせたミアが、どこからか取り出した指輪を手渡してきた。
透明なガラス玉のついた簡素なものだ。
左手の中指にそれをはめる。特に意味はないが、なんとなくその指にはめたいと感じた。
「これでいいのか?」
「はい。そうしてから、こう唱えてください。『エイプル・エイプル・エイプルリン・マジカル・ラブリィ・ドレスアップ』」
「……は? エイ……なんだって?」
「ですから、エイプル・エイプル・エイプルリン・マジカル・ラブリィ・ドレスアップ、です」
さっきまでの決意はどこへやら、オレは今すぐこの場から帰りたくなった。
何が悲しくて、そんな幼児向けアニメのような言葉を口にしなくてはならないのか……。
「ちょ、ちょっと待てよ。それ以外の方法はないのか? せめて、もう少しかっこよさそうな呪文とか……」
「すみません。契約の呪文は、これと決まってしまっているんです……」
「し、仕方ねえなあちくしょう!」
意を決して、大きく息を吸う。
「ちなみに、変身するための呪文もこれなので、今後一番お世話になる呪文になるかと……」
「~~~~~! あーもう、わかったわかったよ! ほんっと世界って間違ってんなクソ! エイプル・エイプル・エイプルリン・マジカル・ラブリィ……ど、ドレス、アーーーップ!」
唱えきった瞬間、目の前に魔方陣が現れて、かと思うと、全身が眩い光に包まれた。
体の内側から、力が溢れ出てくるようなイメージが湧いてくる。
光が収まると――オレの服は制服ではなく、黒いマントとショートパンツに変わっていた。
「こ、これは……」
「契約完了です。これならガイストに対抗し得るだけの力を発揮出来るはずです」
ミアの言葉通り、全身に力がみなぎっている。
先ほどまでの倦怠感がどこかに吹っ飛んだかのようだ。
「すごいな……肌から活力が突き破ってきそうなくらい、力が湧いてくる……」
「魔法の力は、すなわち思いの力です。ですから、今感じているその力は、紛れもなくあなた自身の力ですよ、夏輝さん」
それが本当なら、それほど嬉しいことはない。
「でもなんだよ、このコスチューム……へそ出しってお前、露出度高すぎだろ、これ……しかもなんなんだよ、このメルヘンな感じの星は」
「とっても似合っていると思いますよ?」
似合ってるかどうかが問題じゃない。
腕や脚ならともかく、腹出しルックなんて普段はしないから、少し恥ずかしい、な……。
気を取り直して津久井の方を向くと、奴の視界がちょうど戻ったらしく、オレの姿を見て目をしぱしぱさせていた。
「神田さん……? その姿は、一体?」
「フン、面倒事を引き受けちまったんだよ。迷って出てきた馬鹿をあの世に送り帰すっていう面倒事をな」
取り落とした木刀を拾い上げる。
今回の戦いに臨むにあたって、これ以上の得物はない。
「オレの手で、また眠らせてやるよ! この馬鹿野郎があっ!」
強く地を蹴って、戦略もなにもなく、木刀を振りかぶって突進。
ほんの一歩で相手の懐に飛び込むことができた。
踏み込むの速度が跳ね上がっているのが、自分でもわかる。
「は、はやっ……くううっ!」
力任せの一発に辛うじて反応した津久井は、木刀を盾にしてそれを受ける。
契約の力なのだろうか、さっきまで力負けした相手を、オレはぎりぎりと押し込んでいく。
そのまま腕に力を込めて弾き飛ばし、バランスの崩れたところへ横薙ぎの一閃!
「なっ!?」
変身前と似た展開だが、今度は相手の得物を完全に吹っ飛ばした。
地面に落ちた木刀が、カランカランと空しい音を立てる。
「くそ! これなら!」
最後の抵抗か、津久井の背中から幾本もの腕が伸びて、鞭のように襲い掛かってきた。
それを冷静に木刀で切り払う。
力で勝っていることがわかっている以上、この腕も現時点ではそれほど脅威ではない。
これで津久井に攻め手はなくなった。
この勝負……
「オレの勝ちだ、津久井!」
「そ、そんな、そんなまさか……」
愕然とした表情の津久井は、がっくりと肩を落としてうつむいた。
そんなことなど意に介さず、オレは更に踏み込んで間合いを詰め、木刀を振り上げる。
もうこいつは普通の人間ではないのだ。
どうせあの世に送り帰すのだから、全力でぶっ叩いてもいいだろう。
容赦なく振り下ろそうとした瞬間、津久井がふと顔を上げた。
「まさか……もう勝ったとお思いでしたか」
その言葉を発した口から、白いものが怒涛の勢いで放出された。
それが木刀に絡みつき、更にオレの体をも覆ってくる。
「な、なんだ、これは……!?」
懸命に木刀を振るって払おうとしたが、それは粘着性があり、触れた部分はどんどんくっついて、ついにオレは立っていることもままならなくなって倒れてしまった。
「な、夏輝さん! 今助け……」
「もう邪魔はさせませんよ!」
「きゃあっ!」
駆け寄ろうとしたミアにも、津久井は同じ攻撃を繰り出した。
まるで投網のように広がったそれを、身軽なミアも避け切れず、動きを封じられて地面に転がる。
この白いのは、糸……か?
そして複数の手……まさか、津久井の奴の力は……。
「これは、蜘蛛の糸か……!?」
「今更気付きましたか、神田さん。そうです。僕が得た能力は、蜘蛛の力なんです。腕がたくさんあって、しかも相手の動きをこうして奪ってしまえば、負けようがないでしょう? これも全部、あなたに勝ちたいがために、僕が得た力です」
言っていることはわかる。
確かに、確実に相手に勝とうとしたら、この戦法はなかなか悪くない。
だが、しかし。
「お前、あれほど修行に明け暮れてただろうが……いつか、オレみたいになりたいって言ってたらしいな……」
辛うじて動く首を動かして、視線を津久井に向けて、はっきりと告げる。
「それなら! 正々堂々と! 剣で勝負しろよ! お前の志は、どこに消えた! 津久井ぃ……!」
「……知った風なことを言わないでくださいよ! 僕はあなたに勝てれば、それでいいんです!」
言い終わったかと思うと、津久井の顔に再び下卑た笑みが宿る。
「大人しくしていてください。また搾り取ってあげますからね……フフ」
そこには、もうオレの知っている津久井はいなかった。
初めからそうわかっていたはずなのに、そう再確認させられた。
……津久井。もう戻れないんだな。オレは……悲しいよ。
「くっ……」
津久井はオレの後ろに回ったかと思うと、無理やりショートパンツを剥ぎ取ってきた。
再び局部を露出させられて、かあっと頬が熱くなるのがわかる。
「ち、チ〇コがそんなに見たいのかよ。お前の性癖って、なかなか歪んでんだな」
せめてもの抵抗として、そう罵ってみる。
が、津久井にはそれが逆に滑稽に見えるのか、笑みを全く崩さない。
「神田さんはきれいですから、性別の問題じゃありませんよ。それに、自分より強い相手を弄ぶのは、本当に楽しいですからね……!」
しゅるしゅると、糸がチ〇コに巻き付いてくる。
包み込まれただけで、そこはむくむくと感じ始めてしまっていた。
くそ、ただでさえ敏感な部分なのに、さっき一度イカされたせいで、余計に感じやすくなってやがる……!
「ははは! 本当にこっちは素直ですね! 下半身は準備万端だって言ってますよ!」
「ふ、フン。そこを刺激されたら出ちまうのは、仕方ない。男ってのは、そういう風に出来てるんだからな」
苦しい言い訳だが、嘘ではない。
そのせいか、津久井も一瞬難しそうな顔をして、ふむ、と黙りこくった。
しかし直後、にんまりとした笑顔が戻ってくる。
その表情は、オレの心に影を落とすに十分なものだった。
「それじゃ、こっちの方はどうでしょうね」
「な、なんのこ――にゅああ!?」
唐突に体の中心を貫く刺激を感じ、思わず妙な声をあげてしまった。
津久井が触れた場所は、あろうことかオレの……肛門だった。
臀部の奥にある、ある意味秘められた場所。
そこに、無遠慮に指を突っ込んできたのだ。
「もの欲しそうにひくついてるじゃないですか。ここで感じちゃうなんて、神田さんも相当な好きものですね」
「ち、ちが……!」
「隠さなくていいですよ。ほら、僕の糸はこんなことも出来るんです。よく味わってください……ねっ!」

「やめろ! そんなところ、入らなっ――んぐうぁぁっっ!! くっ、アアッ!」
まるで逸物のようになった糸の塊が、ずぶずぶと菊門に侵入を始めた。
本来は排泄にしか使わない部分。そこを犯されている。
それは、先ほど手コキで強制的に絶頂させられたことよりも、遥かに屈辱を感じさせる行為だった。
「お、おおあ……し、尻に何か、入って……く、るし……」
「その割に、すんなり入っていきますね。実は初めてじゃないとか?」
ギクリ、と体が硬直した。
かつての記憶が蘇りそうになり、すぐに思考を閉じる。
「そんなわけ、あるか。早く、んはぁ、ぬ、抜けよ」
「遠慮しないでくださいよ。動かしてあげますから」
中に入っている糸が、入ったままぎゅるぎゅると回転を始める。
「んはあああ!? なんだよ、これえっ!? と、止めろよおお!!」
まるで、排泄したものがそのまま尻の中に逆流してきているようだ。
それをまた出して、戻ってきて、また出して……。
排泄時に感じる快感を、強制的に連続して味わわされて、オレはもうすっかり涙目だった。
こんな辱めは生まれてから初めてかもしれない。
「んはぁぁぁああ……あは……ふぁぁん……」
今すぐにやめてほしいと思うのに、気持ちよすぎる。
だめだ、流されたらいけない。
でも、排泄時の快感は、それこそ生理現象に他ならない。
感じないようにするなんて、そんなことは不可能だった。
「あはは! すごい! もうビンビンだね神田さん! ほらほら、さっさと観念してくださいよ!」
「んぎゅあああ!!」
必死に堪えようとしているオレを嘲笑うように、チ〇コを包む糸も回転し始める。
亀頭もカリもスジも、全て同時に刺激されて、痙攣が止まらない。
根元の方で、粘液がグツグツと煮えたぎっている。
「も、もう、だめ……」
どれだけ我慢しても、そのときが来るのは時間の問題。
そう思うと、オレの心は一気に崩れてしまった。
灼熱の欲望が一気に尿道をかけ上がってくる。
びゅくくっ! びくんッ! どぶりゅるるっっ!!
「はひゃあああああ!! イク! オレ、イッちまって、ふわぁ! あはぁぁぁああ!! くあ――アアッ!!」
体をピンと弓なりにして、襲い来る快楽を全身で受け入れた。
腰の震えが止まらない。
「……はぁ、んはぁぁぁ……」
精液が止まってからも勃起は治まらず、オレは熱い吐息をこぼした。