それから一月ほど経った、とある土曜日。
僕は高鳴る鼓動を抑えようと胸に手を当てて深呼吸をしました。
少し落ち着いてから、改めて身なりの確認をします。
着てきたのは、お気に入りの花柄ワンピース。
ちゃんと前日にアイロンもかけてきましたし、どこもおかしなところは見当たりません。
意を決して、眼前のアパートの階段を一歩一歩上がっていきます。
二階の一番奥、表札には『桜井』と書かれています。
もう一度大きく息を吸って、ぐっとインターホンを押しました。
『えっ? もう来ちゃった!? はーい! 今出まーす!』
中から慌しい足音が聞こえてきて、直後に目の前の扉が勢いよく開けられました。
「いらっしゃい恭……くん?」
「ど、どうもです」
なんだか気恥ずかしくて、顔を隠すようにお辞儀をします。
稔くんは目を丸くして、ぼくをまじまじと見つめてきます。
あまりじっと見られると、さすがに居心地が悪いです。
「ど、どうしたの恭くん、その格好?」
「変、ですか?」
「へ、変じゃないよ。すごく似合ってる。でもそれが逆に変というか……と、とにかく上がってよ」
促されるまま、ぼくは稔くんの家に上がらせてもらいました。
狭い空間にテーブルと椅子があり、そのすぐ横に台所があります。
ここがアパート……初めて入る建物に、ぼくがつい目移りしてしまいました。
「ご、ごめんね。もう少し遅いかと思って、まだ掃除の途中で汚いと思うんだけど」
「え? いえ、全然そんなことありませんよ」
洗い物はきれいに片付けられていますし、床にも目立った汚れはありません。
「とりあえず、突き当たりの部屋が僕の部屋だから、そこで待ってて。お茶を入れてくるから」
「わかりました」
そう言って廊下を歩いていこうとしたとき、前触れなく玄関の扉が開きました。
「ただいま……ん? ちょうど来客中だったかな」
入ってきたのは、落ち着いた雰囲気のあるお兄さんでした。
スーツを見事に着こなしていて、ぼくらに比べると身長も高く、まさに大人の方といった感じのする人です。
「お兄ちゃん? 今日はやけに帰りが早いんだね」
「会社の機械が急にトラブって止まっちゃってな。仕事にならないから帰らせてもらったんだよ」
「大変だね。あ、紹介するね。今年から同じクラスになった……」
「樋口・恭です。稔くんとはいつも仲良くさせて頂いてます」
「稔の兄の陽介だ。こちらこそ、稔と仲良くしてくれてありがとう」
そう言って、見る人を安心させてくれるような笑みを浮かべてくれました。
ぼくが女の子だったら、一目惚れしていたかもしれません。
それくらい魅力的な笑顔でした。
この陽介さん、きっと女性にもてもてなんでしょうね。
「しかし、稔もやるものだね」
「え? 何が?」
お茶を探しているのか、台所の戸棚をがさごそと漁りながら稔くんが聞きました。
「いやなに、休日にこんなに可愛い女の子を連れ込むようになったんだなってね。稔も男の子なんだな」
「恭くんも男の子だよー?」
「……え?」
陽介さんはきょとんとした顔になりました。
「ほ、本当に?」
「すみません、本当なんです」
ぼくは普通より随分と女の子っぽい顔立ちですし、しかも女の子の格好をしていますから、そう思われるのも仕方がありません。
「ということは、こんなに可愛いのに……ついてるってことか!?」
がしゃん! と台所で稔くんがずっこけたのが見えました。
あまりにストレートな発言に、ぼくもつい赤面してしまいます。
「お、お兄ちゃん! 動揺しすぎ! それに失礼だから!」
「はっ! す、すまない。恭……くん。取り乱してしまって」
「い、いえ、こちらこそすみません。昔から姉のお下がりをよく着ていたもので……」
それに、男物のかっこいい服をぼくが着ると、どうもしっくりこない感じがするのです。
その人に合った服を着るのが一番いいとぼくは思っています。
かっこいい人はかっこいい服を、かわいい人は可愛い服を。
となれば、女の子っぽいぼくが女の子の格好をするのは、それほどおかしなことではないのです。
世間一般とはズレているのは承知していますが、ここは譲れません。
「うーん。お茶切れてるみたい。ちょっと買ってくるね」
「えっ? いいですって稔くん、そんなに気を使ってくれなくても」
「大丈夫、お店すぐ近くだから。部屋で待っててね!」
言うが早いか、稔くんは駆け足で出て行ってしまいました。
なんだか余計な気苦労をかけてしまっている気がして申し訳ないです。
本当に、気を使ってくれなくてよかったのですが。
お茶よりも、稔くんと少しでも長く話したい、というのが本音ですし……。
「稔は君と随分仲良くやれているみたいだね。本当に良かったよ。両親が出張でいないから、俺が保護者代わりなんだけど、仕事があるから普段は構ってあげられないからね。君には感謝しないといけないな」
「いえ、そんな……ぼくが好きでやっていることですから。あ、好きってその、変な意味じゃなくて」
勝手にしどろもどろになるぼくを見て、陽介さんは一瞬目を見開いてから、すぐに柔和な笑みに戻る。
「変な意味でも、別に駄目とは言わないけどね。好きになること自体は、仕方のないことだから。性別が同じだろうが、血が繋がっていようが……ね」
「え? それは、どういう……?」
「おっと、今のは聞き流してくれていいよ。君からはなんとなく似たにおいを感じたから、つい口が滑ってしまったね。とりあえず、稔とはこれからも仲良くしてくれると嬉しいな」
「もちろんです。稔くんのことは、大好きですから」
昔から、とは言いませんでした。言えなかった、の間違いですが。
この気持ちを口に出すのは簡単です。
でも、それを誰に否定されようとも、稔くん本人に否定されたらと思うと、こわい。
女の子だと勘違いしていた頃とは、もう違います。
男の子だとわかってしまって、それでも友情だと断言出来ない、この熱い想い。
これを異常だと稔くんに思われてしまったら、今の関係すら崩れてしまいそうで、それだけは絶対に嫌なのです。
「稔は優しい子だから、きっと君を傷つけたりしないよ。多分、君がそうであるようにね。樋口・恭くん」
ぼくの考えを知ってか知らずか、陽介さんはそんな言葉をかけてくれました。
その言葉の響きがじんわりと胸に広がって……ぼくの顔には、自然と笑顔が戻っていました。
この優しいところ、稔くんになんだか似ています。
やっぱり兄弟なんだなあと、そんなことをしみじみと思いました。
ほんの五分ほどで稔くんは戻ってきました。
熱めのお茶に少しずつ口をつけながら、ぼくらは他愛ない会話に花を咲かせます。
やはり、特に盛り上がったのは恋バナ……いわゆる恋愛面の話でした。
「稔くん、彼女いたことないんですか!? なんか意外です……稔くん、もてそうなのに」
「全然そんなことないよ。お兄ちゃんは物凄くもてるけどね。昔とか、すごかったなあ。バレンタインとか。紙袋いっぱいにチョコレート持ち帰ってきててね。明らかに本命っぽいのも四個か五個くらいあって」
「そ、それは凄まじいですね」
「しかも甘いもの得意じゃないのに、『食べてあげないと失礼だから』って言って、頑張って全部一人で食べてて。子供心に尊敬したよ。次の日、腹痛で休んでたけど」
「ふふっ! あ……すみません笑ってしまって。でも、いいお兄さんじゃありませんか」
「うん、自慢のお兄ちゃんだよ」
一点の曇りもない目で、稔くんは言い切りました。
兄弟のことをそういう風に言えるのはとても良いことです。
「恭くんの方は、彼女いたことないの?」
「ありませんね。仲の良かった女の子は何人もいましたけど、皆友達止まりでした。告白されたことは何度かありましたが……」
「そうなの!? ねえ、どんな人だった?」
「……全部男の子でした」
「……そ、そう」
稔くんは、なんとも言いがたい顔をしましたが、無理もありません。
「まあ、恭くんはかわいいから、ある意味当たり前かもね」
「稔くんだってかわいいじゃありませんか。ぼくが女の子だったら、絶対にアタックしてますよ」
女の子じゃないから、あまり表には出さないようにしていますけど、ね。
「僕も女の子だったら、恭くんにアタックしてたかもね」
「本当ですか!?」
「まあ、男だからしないけどさ。僕、ノーマルだから!」
「で、ですよね」
ほんの少し喜んでしまった自分を恥ずかしく思いました。
男の子同士で……なんて、おかしいですよね。
「僕らもいつかは彼女作ってさ。一緒にデートとかしてみたいよね」
「そう、ですね」
ぼくは彼女を作りたいなんて、今はあまり思いません。
だって、ぼくの好きな人は、女の子じゃありませんから。
どうしてお互い男の子に生まれてきてしまったんでしょうね。
そんなどうしようもないことを、ふと思ってしまいました。
「映画とか行ってみたいなー」
「それじゃ、二人で行ってみますか?」
駄目元で聞いてみました。すると、稔くんは真剣な顔で考え込んで、
「友達と二人で映画とか、憧れではあるけど……金欠病で、なかなか行けないんだよね」
確かに、その問題はあります。
稔くんの性格上、ぼくが奢ると言っても断ってきそうですし……。
しかし、少し考えてから、ピーンと妙案を思いつきました。
「レディースデーを利用しましょう」
「レディースデー?」
「簡単に言えば、女性に限り代金を割り引いてくれるサービスですね」
「僕たち、男の子なんだけど……って、まさか!?」
どうやら察してくれたみたいです。
強く深く、ぼくは頷きました。
「稔くん用の服は、責任を持って用意しますから。とびきりかわいいのを用意しておきますね!!」
幸い、ぼくら二人は顔立ちが女の子寄りです。
きっと女装すれば、余程のことがない限り男の子だと看破されることはないでしょう。
明日は日曜日。稔くんに似合う服を見繕う時間はたっぷりあります。
「ううう……どうしてこんなことに……」
ぼくを見つめる稔くんがなんだか涙目だった気がしましたが、気のせいだと思うことにしました。
少しずつ日が傾いてきた辺りで、その日はおいとますることにしました。
まだ日は長いのですが、あまり遅くなるとお姉ちゃんたちに心配をかけてしまうかもしれませんから。
それに、稔くんたちにも迷惑かもしれません。
性格上、稔くんはそういうことをぼくに言ってこないでしょうから、こちらから遠慮するのがいいでしょう。
「今日はありがとうございました。色々話せて楽しかったです」
「僕もだよ。また学園でね」
「ええ、さようならです」
手を振って別れたぼくの足取りはとても軽いものでした。
こんなに楽しい気分は久しぶりです。
早速帰って、当日着ていく服の見繕いもしておかないと。
思わずスキップしてしまいそうなほどの高揚感に、フッと冷たいものが触れました。
「……?」
ほんの一瞬足を止めて、意識を張ってみますが、特に怪しい気配は感じません。
なんだか誰かに見られていた気がしたのですが、気のせいだったのでしょうか。
楽しい気分に水を差されたような不快感を覚えつつ、ぼくは家路を辿りました。
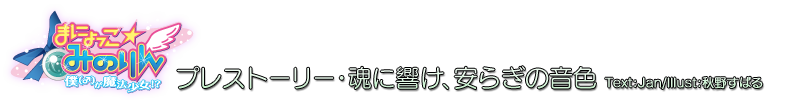
■06