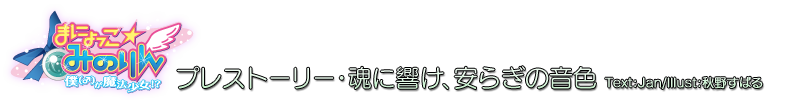ぼくは普段着のスカートをはいて、街を目指していました。
自宅に戻ってから自分の私服を一通り眺めていたのですが、稔くんに似合いそうなものはあまりなかったのです。
ですから、稔くんのために服を買ってあげようと思って外に出たのでした。
もちろん、本当のことを言ったら稔くんが申し訳なく感じてしまうでしょうから、お姉ちゃんのお古ということにしますけどね。
そんなことを考えていたら――ふと、昨日感じたものと同じ気配を感じました。
昨日は確信を持てませんでしたが、今日ははっきりとわかります。
これは間違いなく、人外の気配です。
「そこの娘、少し話がしたいのだが、時間はあるか?」
背後からそんな声が向けられました。
話しかけてくるタイプは珍しいですが、前例がないわけではありません。
とはいえ、相手にしていると面倒ですし、もしも襲われたらぼくに対抗手段はありません。
となれば、三十六計逃げるにしかず。
返事もしないまま、脱兎のごとくぼくは駆け出しました。
「ぬう!? 無視するどころか逃げるとはどういう了見……!」
怒声に近い声が聞こえましたが、それすら無視して走り抜けます。
なぜか今日に限って、ぼく以外の人影が全く見えません。
アレに遭遇する日は、いつもそうでした。
何か不思議な力で、人を遠ざけたりしているのでしょうか。
一つわかることは……ぼくを助けられる人は、ぼくだけだということです。
「はあ、はあ、はあっ……」
どれだけ走ったでしょうか。息を切らして塀に軽く寄りかかりました。
全力疾走なんて久しぶりだったので、足ががくがくと震えます。
元々運動は出来る方ではありませんが、ちょっと走っただけでこれじゃ、さすがに男としては恥ずかしいですね。
思わず苦笑しそうになりましたが、その思考はすぐに中断されることとなりました。
気付くと、目の前にぼんやりとした表情の男性が立っていました。
病的を通り越して、人間的でないほど青白い顔。
焦点の合っていない目は、虚空を彷徨っています。
その視線が、不意にぼくに向きました。
「ひっ……」
体の中心に氷を突っ込まれたかのような恐怖に、呼吸すら忘れそうになりました。
足を動かさず、地面をゆっくり滑るように男性はぼくに近寄ってきます。
逃げ出したいのに、足が動きません。足が根っこにでもなったかのようです。
やがて、すぐ目の前に男性がやってきて、ぼくの顔をスッと覗き込みました。
漆黒に塗り潰された空ろな鏡かと思える瞳に映し出された自分の顔は、今にも泣き出しそうな情けない顔をしていました。
「き、み……の心、誰かで、満ちて、る……き、み、ぼく、みて? ね、え、ぼく、だけ、みて?」
抑揚のない声が、乾いた唇からぽろぽろとこぼれて耳に届きます。
そして、枯れ木のような腕が、ぼくの肩を抱こうと持ち上がって、
「い、やあああ――――!!」
力の限り叫んで、無我夢中でぼくは駆け出しました。
心臓が早鐘を打っています。
あんなおぞましいアレに会ったのは、初めてです。
ニンゲンの形をしたニンゲンでないモノ。
それが、あれほどまでに恐ろしく感じるとは思っていませんでした。
後ろを見ると、男性は無表情のままぼくを追ってきていました。
「助けて、誰か、助けて……!」
誰も助けてなんてくれない、そうとわかっていても、そう言葉が漏れました。
そして、そんなぼくをかつて助けてくれた人が思い浮かびます。
「稔くん、助けて、助けてください……っ」
呪文のように呟きながら、ぼくはひたすら救いを求めて走り続けました。
どこをどう走ったのか、あまり覚えていません。
薄暗い路地裏へと逃げ込んだぼくは、膝を押さえながら息をつきました。
これ以上追いかけてくるようなら、逃げ切れる自信がありません。
稔くんの服を買おうと思って出かけただけなのに、どうしてこんな目に遭うのでしょう。
女装したくなさそうだった稔くんに女装させようとしているから、天罰が下ったのでしょうか。
しかし、今更反省しても後の祭りです。
今は、どうにかしてあの男性から逃げ切るかを考えなければいけません。
とはいっても、ぼくには特別な力はありませんから、足で逃げるしかないのですが……。
そう思っていると、不意にじゃりっと地面を踏みしめる音が聞こえて、ぼくは身を固くしました。
そして、ぼくの前に姿を見せたのは、
「あれ? 恭くん?」
「み……稔、くん?」
制服姿の稔くんでした。
一気に気が抜けて、ぼくはその場にへたりこんでしまいました。
「こんなところでどうしたの? なにかあった?」
「稔くん……稔くん!」
心配そうにぼくを覗き込む稔くんに、ぼくは発作的に抱き付いていました。
押しのけられるかと思いましたが、稔くんの腕がそっと背中に回ってきました。
「大丈夫。怖いことなんてないよ。僕が安心させてあげる」
耳元で優しくささやいてから、稔くんはおもむろにズボンを下ろしました。
既に大きくなった剛直が、空気に触れて小さく震えるのを見て、ぼくは思わず喉を鳴らしそうになりました。
「え!? 稔くん、急にどうしたんですか!?」
「……恭くんは僕とするの、嫌なの?」
「い、嫌じゃない、ですけど」
むしろ、一度でいいからしてみたいって思っていたくらいで。
そう思ったのが表情に出たのか、稔くんはニヤリと意地悪な笑みを浮かべました。
「なら、何も気にすることないよね? ほら、見てよ……今から恭くんと、って思うだけでこんなになっちゃったんだよ」
目の前でピンク色にも見える怒張が、ぴくぴくと動いています。
まるでぼくを誘っているような、いやらしい反応です。
それが稔くん自身であるかと思うと、ついつい見入ってしまいました。
「すごい、稔くんの、おっき……」
ぼくもそれなりの大きさではあるかと思いますが、他の人のをまじまじと見るのは初めてなので、不思議な感銘がありました。
「恭くん、脱がすから、腰浮かせて? もし嫌だったら言ってね」
「嫌、じゃない、ですよ。稔くんなら」
「……ありがとう」
ぼくが微笑むと、稔くんも笑顔を返してくれました。
スカートの下に腕が侵入して、パンツをするりと脱がされます。
膝を持って無理やり股を開かされると、ぼくのおち〇ちんが丸見えになってしまいました。
「あ、あんまり見ないでください」
人にこうして見せるなんて、もちろん初めてのことです。
心臓が強く鳴っていて、胸が痛くなるほどでした。
「恭くんのココ、とってもかわいいよ、ふふ」
言いながら、稔くんはサオの部分にそっと指先を絡ませてきました。
「ひうっ……」
ただそれだけで、ぼくは女の子のような声を漏らしてしまいました。
稔くんが、ぼくのおち〇ちんを触って……っ!
羞恥と快感で頭がぐちゃぐちゃになりそうでした。
「一気に硬くなってきたよ? 僕に触ってもらえるのがそんなに嬉しいの? やらしいなあ恭くん」
「ごめんなさい……でも、ずっと稔くんとこういうことしたいって、思っていたので……」
好きな人とエッチしたい。
思春期の男の子なら、当たり前に考える妄想。
その相手が男の子だったと知ったとき、ぼくがどんなに落胆したか、きっと稔くんにはわからないと思います。
それなのに、こうして一緒にいられることが、どれほどぼくの心を満たしてくれていることでしょうか。
今になって、ようやくはっきりとわかりました。
ぼくは、かつて出会ったみのりちゃんという女の子を好きになったのではなかったのです。
ぼくは、桜井・稔という一人の人間を、愛したのだということを。
だから今、ぼくが泣きたいくらい嬉しいってことくらい、知ってほしいです。
素直にそう思いました。
「それじゃ、このままおち〇ちんいじめてあげようかな」
「ま、待ってください。ぼく、稔くんと一緒に気持ちよくなりたいんです。ぼくだけじゃ、嫌、です」
「そっか。そういうことなら――こっちを使うしかないね」
稔くんの手がおしりの方へとすべっていきます。
その指先がどこに向かっているのか、直感的に理解したと同時に、
「んぐううううううっっ!? うあ!? ああっ!!」
体の中心を衝撃が貫きました。
誰にも、それこそ自分自身ですら一度も見たことのない窄まりを、稔くんは静かに撫で回してきます。
「やあ!! 稔くん、そんなところっ! きたないから、ひああっ!!」
くるくると指が動かされる度に、はしたない声が漏れてしまいます。
今、ぼくの体は完全に稔くんに弄ばれるおもちゃでしかありませんでした。
「恭くんの体に汚いところなんてないよ。それに、恭くん初めてでしょ? ちゃんとほぐしておかないと気持ちよくなれないからね」
確かに、いきなり稔くんのを突っ込まれたら大変なことになりそうです。
ぼくの体を気遣ってくれる辺り、エッチのときも稔くんは優しくて本当に嬉しい、のですが、
「そんなところをいじられるの、恥ずかしいんです……」
「そんなところって、どこ?」
指の動きを止めて、稔くんがそんな意地悪なことを聞いてきました。
黙っていても動いてくれないところを見ると、答えるまで許してくれないみたいです。
「お……おしりの、あな……っぁあああ!」
答えた瞬間、自分で口にした部分に、何かが侵入してきました。
小さくて、小刻みに動いていて、ぼくの体にどんどん入り込んできます。
それが稔くんの指だと気付いたときには、ぼくはすっかり息も絶え絶えになっていました。
「指一本なのにすごく締め付けてくるね。ここに僕のを挿入れたりしたら、食い千切られちゃうんじゃないかな」
こりこりと、指先がぼくの中をかきまわしてきます。
稔くんが、ぼくをおもちゃみたいに弄くりまわしている……。
今だけは、ぼくだけを見てくれてる。
そう思うと、もう触っていないのにぼくの肉棒は恥ずかしいくらいに膨らんでしまいます。
先端からは、透明な汁がとろとろと溢れて、てらてらと光っていました。
「そろそろほぐれてきたかな。恭くんも、これ以上焦らしてほしくなさそうだし……」
軽く前後に指を抜き差ししてから、ゆっくりと指が引き抜かれました。
「んっ、くぅん……」
抜かれるとき、甘い快感が全身を震わせました。
「お願い、します。稔くん、ぼくを、奪ってください」
「もちろんだよ。僕は、恭くんだけのものになってあげる」
その言葉を、ぼくはずっと待っていました。
涙が溢れそうなほど嬉しくて、胸が詰まってしまいます。
そっと、稔くんが剛直の先端をぼくにあてがいました。
「力抜いて」
言われるままに、全身の力を抜いて、大きく深呼吸をしました。
それに合わせるように、それはぼくの中心に向かって突き進んできました。
「んっ……んぐっ、ううっ!! うぎっぁああ!!」
入り口はそこまで痛くもありませんでした。
しかし、先端が入り込もうという辺りになってから、凄まじい圧迫感が襲ってきて、声を堪えることは出来ませんでした。
苦しい、苦しい、息が出来ない!!
内臓そのものが押し上げられているようで、初めて味わう感覚にぼくは為す術がありません。
だけど、苦しいと感じるよりも更に、喜びを強く感じました。
巨大な圧迫感と同じくらい、充足感がありました。
体の中だけでなく、心の中まで稔くんでいっぱいになったかのような、そんな気がして、ぼくは自然と笑みを浮かべて、それを見て稔くんも、ふっと笑いかけてくれました。

「大丈夫? 苦しくない?」
「大丈夫、じゃない、ですよぉ……苦しいに、決まってるじゃない、です、か……」
相手を気遣ってあげる余裕がなくて、つい本音を漏らしてしまいました。
それを聞いた稔くんは、少し苦い顔になりました。
「ええと……抜こうか?」
「今更そんなことしたら、それこそ許しません」
「ええー……」
動くどころか抜くことも許されず、稔くんはなんだか情けない顔になりました。
その顔もかわいかったのですが、あまり困らせてもかわいそうです。
「手を握ってください。そしたら、許してあげます」
「手? こう?」
ぼくが差し出した左手に、稔くんがそっと指を絡めてきます。
細くて白くて、温かい指。愛おしさが溢れそうになります。
まるで幸せな夢が現実になったかのようです。
「稔くん、動いてもいいですよ。そのままだと辛いでしょう?」
「うん……出来るだけ、ゆっくり動くから」
稔くんが静かに腰を前後に揺らし始めました。
引かれると、体の内側が引きずり出されそうな錯覚に、思わず眉間が歪みます。
本来出すだけの場所に無理やり突っ込んでいるのですから、いくら慣らしたとはいっても、さすがに多少の辛さはありました。
それでも、稔くんを気持ちよくしてあげられる。
そう思うだけで、この辛さがまるで気にならないほどの多幸感が胸の内に湧き上がってくるのでした。
「はあ、はあっ、すごい、恭くんのなか、きつくて、うねうねって、気持ちよすぎ……!!」
「あ、ありがとうございますっ! 稔くんにそう言ってもらえるだけで、ぼく、ぼくっ!」
軽く絶頂してしまって、ぴゅるっと白い液体がおち〇ちんから飛び出してしまいました。
「や、やぁだ……ぼくも、なんだかよくなって、あっ、あはぁぁ……!」
ぐちゅ、ずぷ、ず、ずずっ、ずっぷ!
次第に稔くんの腰の動きも早まってきて、最後のときが近いことを知らせてくれます。
ぼくの体力を気遣って早く終わらせようとしてくれたのか、それとも稔くん自身が我慢できなくなったのか。
「恭くん! もう出ちゃう! 出る、出るよ!」
「いいですよ! ぼくの中でイッてください! たくさん出してください!」
「うっ、うああああっ!! あああぁぁ……はぁぁ……」
ああ、出てる……ぼくの中で、どくんどくんって脈打ってるのがわかります。
ぼくの中が、稔くんで満たされていく。
それと同時に、ぼくのおち〇ちんからも、白濁とした汁がどぷどぷと溢れました。
爆発するような快楽ではなく、そのままとろけてしまいそうな、甘い絶頂。
そっと目を閉じて、ぼくはその感覚を忘れないようにしっかりと感じました。
これが、ぼくがずっと望んでいた瞬間。
最高に理想的で幸せな夢なんですね……。