行為が終わって、お互いに服を着直してから、なんとなく二人とも無言でした。
ぼくも、多分相手も、なんて声をかけたらいいかわからなかったのでしょう。
「しちゃった、ね」
最初に口を開いたのは、相手の方でした。
ぼくも静かに頷いて、
「そう、ですね。感謝してます。稔くんとはこういうこと、絶対に出来ないって思ってましたから」
「男の子同士だから、だよね。でも、もういいんだよ。これからはずっと一緒にいるから。恭くんのものになってあげるから」
「はい。ありがとうございます」
そう答えたぼくを抱きしめようと、腕がゆっくり伸びてきて。
微笑んだままぼくは――それをそっと押し止めました。
「恭、くん?」
「……あなたには感謝しています。素敵な夢を見せて頂いて。本当に感謝しているんですよ、ぼくは。だけど」
それでも、わかってしまったから。
「あなたは、稔くんではありませんから。一緒にいてあげることは出来ません」
稔くん――の姿をしたその人は、途端に無表情になりました。
その顔が、中心からピシリとひび割れて、ぼろぼろと崩れていきます。
偽りの仮面が崩れ去り、その下から出てきたのは、先ほど出会った男性の虚ろな目でした。
「どう、して……?」
わかったのか、と言いたいのでしょうか。
「稔くんは、ノーマルなんですよ。友達としてならともかく、男であるぼくのものになんて、なってくれません。それに本物の稔くんなら、あんな意地悪なこと……してほしくても、してくれないと思いますから」
良くも悪くも、ぼくが好きになった稔くんはそういう人だ。
男の子にはさほど興味はなくて、誰にでも優しい。
ぼくだけのものになってくれたらって、再会してから何度思ったでしょう。
さっきまで男性が化けていた稔くんは、まさにぼくの理想の稔くんでした。
だからこそ最初、彼に追われていて半ば混乱気味だったぼくは、本能のままに『理想の稔くん』にすがりつき、行為に及ぶことをよしとしまったのです。
彼はぼくの理想をしっかり体現してくれました。
少し意地悪で、攻めっ気があって、だけど優しい、ぼくだけの稔くん……。
だけどそのために、本物ではないと強く感じてしまったのでした。
「あなたは、ぼくに幸せな夢を見せてくれました。あなたを悪い人だと思いたくないんです。どうしてぼくを狙うんですか? 良かったら、話してください」
「う、うう……うううう!」
男性はぶるぶる肩を震わせたかと思うと、漆黒の瞳からはらはらと涙を流し始めました。
すると突然、男性はぼくの肩に掴みかかってきました。
ぼくの力では、ぴくりとも身動きが取れません。
「なん、で、ぼ、くだけ、みてくれな、いの? ね、え、なん、で? ねえ、」
まともに話が通じそうにはありません。
(せめてぼくに、かつての稔くんのような力があれば……!)
ないものねだりをしてもしかたがありません。
なんとかこの拘束から抜け出せないものかと身をよじろうとしますが、力ではどうにもならないようでした。
やはりぼくではどうすることも出来ないのでしょうか……そう思ったときでした。
――スパァン!
突如頭上から何かが飛んできて、男性の顔を直撃しました。
バランスを崩した男性は、地面をごろごろと転がって、ぴくりとも動かなくなりました。
「ふう、ようやく見つけたぞ、娘。間一髪だったのではないか? 我に感謝することだな」
空から飛来して、そんなことを言う声は、今日最初に聞いたものと同じでした。
漆黒の体を持った彼の姿は、どこからどう見ても、
「……カラスさん?」
しかも、なぜか葉巻をくわえていて、サングラスまでかけています。
よく見ると、足が三本あるようにも見えますね。
「我が喋っていても驚かぬか。なかなか肝の据わった奴だな、娘」
「あの、娘ではないんですけど……?」
「ふむ。しかしながら、我はまだ貴様の名を知らんのでな。名はなんという?」
「ひ、樋口・恭です」
「恭か。我はレイヴンという。以後よろしく頼むぞ」
レイヴン……確か、ワタリガラスの英語名だったでしょうか。
あまりにそのままなネーミングですね。
どうせなら、もっとかわいい名前をつけたら良かったと思います。カーくん、とか。
「恭よ。助けてやる代わりに、我と契約を結んではくれぬか?」
「けい、契約?」
「うむ。貴様に力を与えてやろうではないか……魔法少女としての力を!」
「ま、魔法少女!? 待ってください、一体何の話ですか!?」
突然そんなことを言われても、わけがわかりません。
そもそもカラスが喋っていて、葉巻にサングラスというだけでも意味不明です。
それに、ぼくは男の子なので、正確には魔法少年だと思います。
「その前に、説明してください。あなたは何者なんですか?」
「ふむ。有体に言えば、我は天界より遣われし天使なのだ。そして、あそこに転がっているのはガイスト。この世界に未練を残したまま命を落とした人間の魂……いわば悪霊だな。奴らは生きている人間の魔力を糧とする。そのため貴様のような強い魔力の持ち主に引かれて襲ってくるというわけだ」
「……なるほど」
だから子供の頃から、ぼくは襲われることが多かったわけですね。
これまで不思議に思っていましたが、ようやく合点がいきました。
「だがせっかく強い力を持っていても、使い方を知らぬのであれば宝の持ち腐れよ。身を守るためにも、我と契約して損はないと思うが?」
守る。
そう聞いて、ぼくは真っ直ぐに彼――レイヴンに向かい合いました。
「あなたと契約すれば、力が手に入るんですね。守るための力が」
「約束しよう」
「それなら……ぼくはあなたと、契約します」
ニヤリ、とレイヴンは口の端を吊り上げました。
「ならば、これを好きな指にはめるがいい」
そう言って彼が差し出してきたのは、どこかで見た覚えのある指輪でした。
(これって……)
ぼくの中で、パズルのピースが一つ組み合わさったような感覚がありました。
そうか、あの日稔くんが拾い、そしてぼくが拾ったあの指輪は、これと同じものだったのでは……?
頭の隅でそんなことを思いながら、ぼくは受け取った指輪を左手の薬指にはめました。
指輪といったら、この指以外にありません。
「そうしたら、こう唱えるのだ。『エイプル・エイプル・エイプルリン・マジカル・ラブリィ・ドレスアップ』と!」
「わかりました。エイプル・エイプル・エイプルリン……マジカル・ラブリィ……ドレスアップ!」
瞬間、体の内側で何かが弾けたような気がしました。
指輪から緑色の光が溢れ出して、目の前の全てを覆っていきます。
(この光……力強くて、暖かい……全身に力がみなぎってきます……!)
やがて光が収まると、ぼくの服はいつの間にか変化していました。
緑を基調としたカラーリングの、軍楽隊のような衣装。
スカートはふわっとしたミニスカートで、とても可愛らしいデザインです。
「これは、もしかしてぼく、変身したんですか?」
「いかにも」
テレビや漫画の中でしか見たことのなかった力を、まさか自分が手にするなんて考えもしませんでした。
今までは、普通の人に見えないものが見える、というだけでしたから。
変身出来るなんて、すごいです……これが魔法の力……!
「契約は完了した。あとはガイストを浄化するだけだな、恭よ」
「浄化とはいっても、どうすればいいんですか?」
魔法少女(魔法少年?)としての力は手に入ったようですが、肝心の魔法の使い方がさっぱりわかりません。
「まずは魔法のステッキを発現させるのだ。普段自分の使い慣れているものをイメージしろ。そうすれば最も合っている武器が現れるはずだ」
ぼくが普段使い慣れているもの……?
そう言われてイメージするものといったら、一つしかありませんでした。
(お願い、出てきてください……!)
意識したと同時に、手元に光が溢れました。
その光はやがて形となって、ぼくの手のひらにすっと納まります。
「ほう、トランペットか。なかなかクールだな」
「ええと、それで、どうすればいいですか?」
使い慣れたものが出てきてくれたところまではいいですが、これで戦えと言われても困ってしまいます。
まさかトランペットで殴りつけるわけにもいきませんし……。
「そう気負わずとも良い。いいか恭、魔法というのは、思いがそのまま力となる。貴様の思いが力となり、魔法となる。そう……音楽と同じだ」
音楽と同じ……。
そう考えれば、なんとなくわかる気がします。
ぼくは一体、目の前に転がる男性を、どうしたいのでしょう。
倒したいのでしょうか。助けたいのでしょうか。
答えはもう、決まっています。
「あなたは、自分だけを好きになってくれる誰かがほしかったんですよね」
「う、うう、ああ」
言葉にならないまま、男性は小さく頷いたように見えました。
「ぼくは、あなただけを好きにはなってあげられません。でも、この一曲だけは、あなただけのために、あなたの幸せだけを祈って吹きます。だから、聴いてください」
誰かに愛してほしい気持ち。それは誰だってもっているもの。
それが叶わなかった悲しみは、一体どれほどのものでしょう。
好きな人と一緒にはなれない、そうわかっているぼくには、ほんの少しだけわかる気がします。
そのせいか、耳に流れ込んでくるトランペットの音色は、まるでぼく自身を慰めているようでもあって。
知らずのうちに、頬を熱い涙が伝っていました。
……気が付くと、目の前に男性の姿はなく、辺りには静けさが漂っていました。
ぱちぱち、と小さな拍手が横で起こります。
「ブラボーだ恭。心のこもった素晴らしい演奏だった。うむ、実にクールだ」
「ありがとうございます。あの人は……どうなったのですか?」
「貴様の心が伝わって、未練がなくなったのだろうな。納得したような顔で天に還っていった。フフ、まさに音楽の魔法よな」
音楽は人の心、魂さえも救うことが出来る。
それを証明することが出来て、ぼくも思わず口元を綻ばせました。
「これもレイヴンのおかげですね。ぼくはまだまだ未熟者ですが、よろしくお願いします」
「うむ。こちらこそな」
ぼくはレイヴンと強く握手を交わしました。
この力があれば、ぼくは自分で自分を守れます。
いえ、今度はぼくが稔くんを守ることだって出来るはずです。
ぼくだって男の子です。守られるばかりではなく、守ってあげたい。
「実は、あのガイストは天界から逃げ出した内の一人でな。まだまだガイストは他にいる。我の任務は、それらを天界へ送り還すことなのだ。パートナーとして、これからもよろしく頼む」
「はい。こちらこそです。……って、さっきと同じこと言ってますね、ぼくたち」
「む? ……フフ、確かにそうだな」
カアカアとレイヴンは高らかに笑い声をあげました。
出会ったばかりですが、彼とは上手く付き合っていけそうな気がします。
「それにしても、一人称が『ぼく』という女子は新鮮だな。まあ、別段気にするほどのことではないが」
「あの、さっきも言おうとしたんですが、ぼくは男ですよ?」
はあ? といったようにレイヴンは口をヘの字に曲げる。
「冗談も休み休み言え」
「それが本当なんです」
「何をバカなことを……」
そう言いながら、レイヴンはぼくを真っ直ぐに見上げました。
羽を顎の辺りにやって、なにやら考え込むような仕草をしています。
かと思うと、急に口を開いて、
「失礼する」
え、と思う間もなく、レイヴンはトコトコとぼくの足元にやってきて――
何の迷いもなく、スカートをめくりあげました。
当然そこには、パンツを押し上げるぼくのおち〇ちんがあるわけで、
「きゃああっ!?」
「……ぐわあ!? き、貴様、男だったのカァー!?」
「だから最初からそうだって言ってるじゃありませんかっ!」
「紛らわしい! その顔で女装趣味か! この変態が!」
「な、なあっ……! 勝手に誤解しておきながら、その言い方はひどいんじゃありませんか!?」
……こうして、ぼくとレイヴンの、奇妙な凸凹コンビが出来上がったのでした。
了
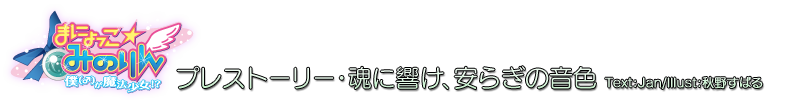
■08